
(最後までスクロールしろよ)
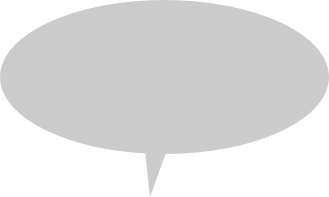
人間の生き埋め
鉄道の架橋・トンネル工事に、いわゆる人柱を建てた話は、全国各地にある。 北海道の場合、人柱はタコ労働者にきまって いた。 オホーツク地域だけでも、常紋トンネルのほか、常呂川、湧別川、斜里町越川の鉄橋が有名である。 旭川の石狩川第一鉄橋や、今金の白川鉄橋にも、 人柱伝説はあるが、常紋トンネル以外、人柱の実在を証明するものはまだ出ていない。
人柱の思想は、日本の古代からのものだと『世界大百科事典』(平凡社)は述べている。
「人柱 人身御供の一種。 架橋、築堤、築城など大工事の際、柱の強化の目的で生きながら人身を沈めることをいう。 これ を水神や地神に奉るのだという説もあり、そのような観念も伴っているが、宗教民族学的起源は、柱の強化のために人身のもつ霊質を柱に移転しようとしたこと にあるらしい。 ……日本には人柱物語が多く、伝説としてひろく全国に語られている」
として、仁徳時の茨田堤、摂津長柄の橋、『平家物語』の経が島、また伊予の大洲と出雲松江城の人柱伝説をあげ、さらに人骨が出てきた例を紹介している。
「かつて皇居の二番櫓の下から人骨が出て、人柱か否かが問題になったことがある。 人柱の物語は史実としてよりも、むしろ 物語としての要素が強い。 それはかつて水神に仕える巫女が、人柱の物語を語り歩いたため、各地の伝説が複雑でありながら、よく符合しているのだともみら れている」
人柱の事実を否定してはいないが、物語として広まっている傾向が強い、との指摘である。
では北海道のタコにまつわる人柱伝説は、事実ではなく物語であろうか。 常紋トンネルのレンガの壁裏から出た「立った姿 の人骨」は「人柱」が物語ではなく事実であることを証明した。 この人柱が、トンネルの壁を強くするという宗教的観念にもとづくものか、みせしめのための 「生き埋め」かはまだわかっていない。
「人柱」以外に「生き埋め」にするところを見た人、または聞いた人はいないかと、私は車を走らせて道内各地を探し歩いた。 新聞記者の「夜討ち朝駆け」みたいに、勤務の前後の時間も利用して、飛び回った。
そのうちに、石北線ではなく、北見から十勝国の池田へ通ずる国鉄池北線の置戸で、常紋トンネル工事に出た人を見つけた。 置戸町秋田団体(地名)の由*鶴造さん(1894・明27年、秋田県生まれ)である。 由*さんは1911(明治44)年に11歳のとき、置戸に入った 集団入植者のひとりだった。 集団入植者は故郷の県名などをとって、秋田団体、雄勝団体の地名をつけた。 二つの団体は、常紋トンネルから西方の近いとこ ろにあった。
話はそれるが、同じ常紋トンネルの東にある佐呂間町栃木団体は、足尾鉱毒で村をうばわれた渡良瀬川流域の元谷中村村長 96戸が1911(明治44)年に集団入植したところだった。 栃木団体の入口には他の集団入植地では見られない交番がたてられた。 田中正造と農家とを 切り離そうとの政府と県との奸策で、この地に入植させられた鉱毒移民は、一年間で半減し、残った指導者は死の病床に臥してまで、「騙された! かえるん だ!」と、うわごとを言い続けた。
原野に入植し、うっそうたる密林を切り倒し、開墾して自立するまでの生活を、入植者は出面取り(出稼ぎ)でまかなった。 冬期間は造材人夫として働いて金をため、夏場に開墾したのである。 秋田団体の由*さんも、入植した翌年の1912(大正元)年に、始まったばかりの常 紋トンネル工事に、山子(きこりで、親方の飯場で働く子方)として入った。 トンネルに使うレンガ(野幌のレンガ工場から運んだ)を洗う湯沸かしの薪をつ くる仕事だった。 由*さんは腕がよく、日に五しき(一しきは高さ約1メートル、幅約2メートル)は切り出したという。
由*さんの入った飯場は信用人夫(前借金をせず、拘束されない自由契約人夫)ばかりだったから、タコと直接話すことはなかったという。 タコ部屋は、信用人夫の真向かいの、トンネルに一番近い沢にたっていた。
由*さんはこう語った。
「飯場では、よくこんな話をしてたな。
『ゆんべ、またやられたんだってな。 前の晩も2、3人やられたそうだな』
みんなの話だと、タコが病気で助からねえと思ったり、工事の邪魔になると思ったら、土をトロッコに4、5杯用意しておいて、生き埋めにしたって言ってたな。 わしは、ほんとうに生き埋めにしたと、信じるな」
直接の目撃者ではなかったが、長く置戸町議をやり、副議長も務めた由*さんが、「生き埋めにしたにちがいない」と語る言葉には、真実みがこもっていた。 その後訪ねた報道関係者に対しても、由*さんは「生き埋めがあったことは確信している」と述べた。
その後私は、置戸町労協の集まりで、「地域の歴史から学ぶもの」と題して、タコ労働について講演した。 しばらくして、 置戸町の老人ホーム入園者の中にタコ部屋経験者がおり、「生き埋め」を目撃していることを知らされた。 藤*房太郎さん(1886・明19年、岩手県生ま れ)である。
藤*さんは1914(大正3)年に厚岸(釧路市の東隣り)の根室本線鉄道工事に出た。 三つあるトンネルの釧路側から三 つ目の尾幌トンネルの工事現場に、大工だったので木挽きの信用人夫として、親方と二人で入った。 旭川の荒*組の飯場だったが、由*さんと違って信用人夫 でもタコ部屋暮らしだった。 88歳になる藤*さんは、ゆっくりした口調で語った。
「わしはいやでな、出たいと言ったんだけど、親方が不承知で、二ヶ月くらいタコ部屋にいたな。 タコはな、生きてんのも死 んだのも、土に埋められるんだ。 それが商売で、毎日埋めるのがいた。 ああいうのは、鬼でもできやしない。 タコをな、トロッコにのせてな、板の上から 突っ放すんだ。 傾斜がかかってるから、無人でもスピードついてな、埋め立てのはずれで脱線転覆するわけさな。 放り出された死体に、トロッコで土をかぶ せる。 ずいぶんたくさん、埋められるのを見たな。 死んだタコの手足が突っ張ってな、トロッコの箱から飛び出してたな。
生きてるタコでも、弱いもんはトロッコに積まれたな。 反抗? そんなことできるもんかね。 呼んだって誰も助けに来 ちゃくんねえしな。 蛇ににらまれた蛙みたいに観念しちまって、積まれて、埋められちまうんだ。 そうやって、見せしめにされて、稼がされ(働かされ)て たな」
藤*さんから私は話を2回聞いたが、2度目はNTVが取材し全国放映した。 3度目に行ったときには、老人性早発痴呆症にかかった藤*さんは、過去を思い出すことが困難になっていた。
タコ部屋関係者の聞き取り調査をしていて、一度目には元気だったのに、二度ないし三度めにはなくなってしまわれた方の数は、五指にものぼる。 タコ部屋調査のタイム・リミットが迫っていることを、痛感させられた。
常紋トンネル工事の死亡者数を、役場や法務局に行って調べたが、無駄だった。 1914(大正3)年に取締令(後述)が出るまでは、官憲の監督はほとんどなく、死体遺棄や「生き埋め」は公然と行われていたようである。
鈴*さん(1904・明37年生まれ)は、タコの運び屋をやった人だけに、タコ部屋の内情に精通していたが、数ヶ月後に再び斜里町の*亮一氏が訪問したときには、なくなっていた。 鈴*さんは生前、
「タコ部屋では、病気のタコは飯場に置かずに、工事現場の隅っこにむしろを敷いて寝かせていた。 タコたちへの見せしめの 意味と、監督の目のとどくところにタコを集めておくためだ。 ひとりの病人のため、監視を飯場にのこすことは、現場の監視が手薄になるからやらなかった。
私はタコをイトムカ(留辺蘂町の山奥にある水銀鉱山)や根北線(根室国と 北見国を結ぶ鉄道で、1937年に着工し、越川鉄橋など架橋したが、三年後の1940年に工事は中止され、開通しなかった)にも運んだ。 怠けていると棒 でたたき、死ねば現場に埋めたものだ。 根北線の越川鉄橋(斜里町)のピヤ(橋脚)には、何人ものタコが“人柱”にされて埋められている」
越川鉄橋工事にくわしいはずの鈴*さんの「遺言」だけに」地元の人たちは*さんを中心に、この地の発掘調査の計画を進めている。
生き埋めのリンチを目撃した人に、網走支庁丸瀬布町に勤める高*清隆さん(1914・大3年生まれ)がいる。
高*さんがタコのリンチを見たのは、小学校6年生の1926(大正15)年の夏7月ごろだった。 家が石北線(北見・遠 軽・旭川)の線路近くにあった高*さんは、湿地を埋めるのに、上手の丸瀬布駅近くの高い所の土を切り崩してトロッコで運ぶ工事を毎日みていた。 飯場は小 金川橋のそばにあって、50人くらいのタコがいた。 工事は地崎組の請負だったが、誰が下請けだったかは、高*さんは知らない。
1974年8月、高*さんと秋*実氏(『丸瀬布町史』編纂者)と私の三人で現場を訪ねた。 高*さんはこう語った。
「残酷なもんでしたね。 タコの肩が破れてウジがわいてるんです。 それでも休ませないんです。 疲れても休ませないで、逆に蹴飛ばすんです。
生き埋めを見たのは国道からで、現場の線路からは10メートルもない近さでした。 タコが二人でトロッコを押してきて、 上の箱をはずす時だったんです。 一人のタコを棒頭が蹴飛ばして倒してから、なんども棒で殴りつけ、倒れたタコのうえに、トロッコの土をかけるように、棒 頭が命令するんです。 情け容赦なく、かけさせるんです」
一台のトロッコの土だけではないんです。二台目も、三台目もなんです。 土工夫は路床のここんとこ(現地を指さす)へ埋められてしまったんです。 それからは、ここを通ると生き埋めの光景が目に浮かんで、気味が悪くてね。
あのタコは成仏できたんでしょうか」
高*さんが指さしたところは、心なしか高く見え、まだ埋まっているようだった。 カボチャのつるがのびて、小高くなっているその土をおおっていた。
こうして「常紋トンネル」の調査が進むにつれ、卒塔婆をたてて供養したという前述の川*組の川*徳四郎さんの証言がますます重要性をもってきた。 常紋トンネルの「生き埋め」を知ってる人は、川*さん以外にはいなかった。
しかし生田原の金山の仕事で儲けた川*組は、1942(昭和17)年の金の生産停止で落ち目になり、戦後、囚人を使って 道路工事に失敗し、川*さんは行方しれずになっていた。 それに1887(明治20)年生まれということから、多分、なくなったのではないかという人が多 かった。 ところが、川*徳四郎さんは登別温泉近くに現存していることがわかった。
川*さんの家を訪ねると、老夫婦でひっそりと暮らしていた。 モルタルも塗らない板壁、凍上であかない奥の室など、質素 な家だった。 羽振りのよい生田原時代には、300人ものタコを使い、戦争中には多額の軍事献金をして数十枚の表彰状をもらい、親方として鳴らした当時の 面影はなかった。
88歳になった川*さんは、数年前から脳軟化症にかかり、記憶もうすれ、ソファにもたれていた。 質問には主として奥さんのしんさん(72歳)が答えた。
川*さんは山形県米沢の川*徳弥・ちゑの三男として生まれ、1906(明治39)年に19歳で家を飛び出し、着物姿に下 駄履きで北海道に渡り、函館から歩いて札幌に着き、偶然拾われたところが地*組だった。 やがて初代地*宇三郎から、契約書に判を押す以外の仕事をまかさ れるほどに信用され、初代宇三郎の母の世話で、地*の下請け川*組のしんさんと結婚したという。 常紋トンネルの工事は、水が悪くて脚気がたくさん出て、 あのへんで人夫さんを大勢殺したという話は聞いて知っている、としんさんは語った。 常紋でタコ供養をしたのではないかという肝腎の質問に対しては、
「関係のないところに供養するはずはありませんから、地*組が関係した工事で、川*はおぼえていたんでしょう」
と語った。
だが私は、常紋トンネル工事請負者名に、地*組の名がないことから、信じ切れない気持ちだったが、脳軟化症の川*さんに、聞きただすことはできなかった。
二度目に川*さん夫婦を訪ねたときには、病人の川*さんまでが「あなた方は警察の人ですか」と言いだし、ご夫妻は私を警戒して口をつぐんでしまう始末であった。
仕方なくあきらめ、辞去しようとして私は、
「今年はなんとかして、常紋トンネルで死んだタコの遺骨を掘り出して、供養したいと思ってるんです。 むかし川*さんが阿*さんをつれて、卒塔婆を建てたように」
と言ったところ、病気の川*さんは突然、
「おれも行く」
と叫ぶように言うなり、ソファから立ち上がろうとした。 脳軟化症で、ほとんど口もきかずにいた川*さんのこの挙動は、彼の心の中に何か思い詰めたものがあるように思わせた。
私の帰宅を追うように、登別から「供養のたしに使ってください」という現金書留がとどいた。
川*さんが常紋トンネルに卒塔婆をたてた謎を知っていた人がいた。 山*さん(1900・明3年生まれ)で、氏は 1937(昭和12)年に小樽から移ってきて、帝国産金の仕事をしていた川*さんの元で働いた人であった。 山*さんは、二度目の聞き取りに訪れたカメラ マンの沢*彰氏に、硬い唇を開いて語った。 当時はどこの金山も好景気だったので、川*さんも「ポッケにお金がなんぼあるのかわからないくらい」だった が、「人がいいもんだから、皆飲まれちまった」と山*さんは言う。
「17年の金の生産ストップから、川*さんはさっぱりダメになり、あとの仕事はみな裏目に出ちまった」とも言った。
「わたしは川*組の不寝番をやってたが、バクチは朝まで許したが、翌朝起きられない奴の尻を棒頭がボッコで叩くときの、凄いのと言ったらない。
逃げたタコをおっかけて常紋へ行ったが、雨が降るときはリンが光るの。 トンネル工事のとき、トンネルのこっちがわにタコ部屋があったの。 水が悪いんですよ、それで脚気なんか酷かったそうです。
常紋トンネルをやるときに、旭川の荒*初太郎さんという人の請負でね、あそこを川*さんが手伝ったんだわ。 あそこをしばらく手伝ったんだと言ってたわ。 今でも荒*組はありますね。 常紋へ来たときは、荒*さんの手伝いで来たんだわ」
山*さんの証言で、川*さんが1912~14(大正元~3)年の常紋トンネル工事に加わっていたことがわかった。 当 時、鉄道の指定請負業者でなかった地*組は、郷土の先輩にあたる荒*組の下請けをやっていたものと思われる。 川*さんはそのときタコの生き埋めを見てお り、二十数年後に常紋近くの生田原の金山に来たとき、供養したのであろう。
「常紋で死んだタコの遺骨を発掘して供養する」と私が語ったとき、「俺も行く」と叫んだ川*さんの心の中を去来したものは、生き埋めにされたタコだったのではあるまいか。
常紋の地獄絵に接して長い間苦悩し、タコの冥福を祈ってきた川*徳四郎さんに出会ったことで私は、加害者であるとのみ考えてきたタコ部屋の親方にも、被害者の側面があるのではないかと思い始めた。
出典:「北辺に斃れたタコ労働者」
小池喜孝 著
HITOBASHIRA図書室
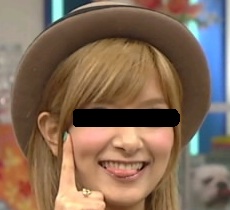
ローラだよ!
HITOBASHIRAのキャラクター辞典を入荷!これからどんどん増えるよ!
NEW!
画像でみてみよう!人柱!

ここから先はよりDeep(ディープ)に、もっと人柱を知りたい人向けのきっかけ的入門案内だよ!

↓ クリック!
↓ クリック!
↓ クリック!